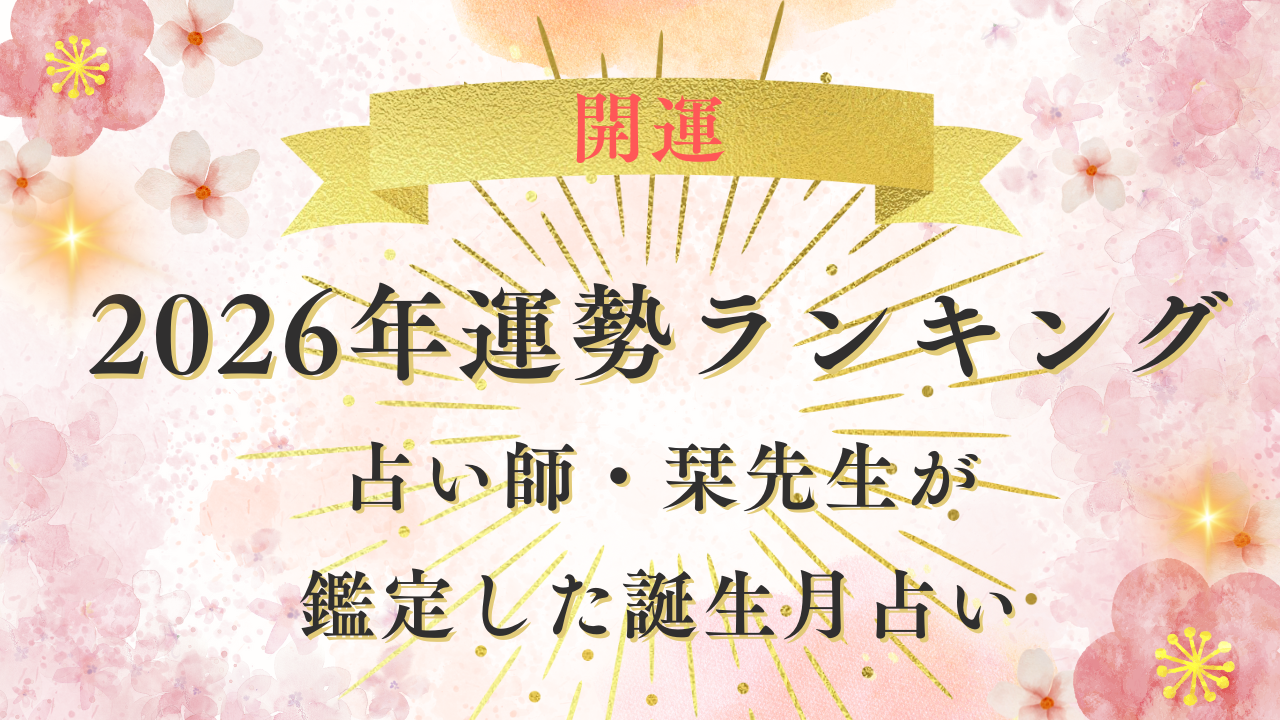【インタビュー】「いま、作れてよかった」。藤原さくらが10周年を彩るアルバム「uku」をリリース。音楽と対峙し解放された彼女が織りなす極上の作品群について、その魅力に迫る。

藤原さくらが前作『wood mood』(2024)から約2年ぶりとなる ニューアルバム『uku』を、2月18日(水)にリリースする。今作は、彼女の10年の歩みと現在地を、より立体的に映し出した作品であり、藤原さくらという1人のシンガーソングライターの血が細部まで通った極めて優れた作品群に仕上がっている。今回Lotusでは、10周年を迎えた彼女にインタビューを敢行し、『uku』の成り立ちについてはもちろん、間近に迫るキャリア初武道館公演について、そして公開を控える映画『結局珈琲』についてなど、たっぷりと話を聞いた。
藤原さくらにとって音楽とは
10th Anniversaryですね。10年間、音楽と対峙し、藤原さんの中で音楽とはどういう存在になっていますか?

藤原さくら(以下、藤原):私にとって音楽は、その時々で興味があることや伝えたいことを一番伝えやすい手段だなと思っています。私が音楽を好きな理由って直感的というか、聴いていたら楽しいとか、そういう感じなんですよ。もちろん良い歌詞に触れて涙することもあるんですけど、それよりは、何を歌っているのかも分からない音楽を聴いて興奮したり……、だから、クラシックやインストを好んで聴く人に近い感覚なのかも。「この楽器はなんだろう?」とか、音自体の方に好奇心が湧くタイプですね。「今度はこの楽器を使って曲を作ってみたい」、「次はこのリズムで曲を作ってみたい」という私の好奇心を発散できるのが、音楽だと思います。
では、何か固定のジャンルで音楽を聴くというよりは、ボーダーレスに耳馴染みのいいものを選んでこられた?
藤原:はい。だから好きなジャンルもバラバラなんですよね。デビューしたての頃は、アコースティックで、カントリーっぽいアルバムからスタートしたのですが、Ovallの皆さんとご一緒し始めてからは、HIPHOPにも興味が湧いて。今作では、ジャズやサルサ。本当にジャンルレスにその時、興味がある、自分がやってみたい音楽っていうものを表現してきたなと思いますね。
なるほど。
藤原:ジャンルレスって、シンガーソングライターだからやりやすいことというか。例えば、バンドなら色もそれぞれありますし、求められることも固まってきたりもする。シンガーソングライターだからこそ、作品ごとにいろんなことに挑戦できる。そういう環境が私の性格には合っているのかなと思います。
ジャンルに囚われることなく歩んだ10年間。活動当初、想像していた未来像に近づいているのか、そういった実感についても聞いていいですか?
藤原:10年前か……。ただ、当初からいろんなことをやってみたいとは思っていたんですよ。音楽のサイクルってどうしても決まっていて、制作をして、リリースしたら、リリースイベントやツアーを回って、ひと段落ついたらまた制作を始めるといった感じで……。私はいろんなことをして、そこから受ける刺激の中で音楽が生まれるタイプだったので。音楽じゃないことも色々やっていきたいと思ってました。文章を書くお仕事やラジオでお話することも好きだったし、お芝居をしてみたり。その時々でやりたいことをやっていると、自然と「こういうお仕事には興味がありますか?」と思ってもなかったところからお仕事がやってくることが多くなったんです。だから、10年前に想像していた通りにはいい意味でなってないかもしれません。
本当に色々なお仕事を真摯にやられている印象があります。
藤原:「私ってこういうこともできるんだ」とか「でもこれは本当に向いてないな」とか、そういうことを試行錯誤しながらやってきた10年間だったなと思います。
音楽をやっていたらそこに付随するさまざまなことにも挑戦できた。
藤原:そうですね。基本的に面白そうと思ったものは1度はやってみたいタイプなんです。だから自分の性分にあった働き方をしてこれたなという自負はあります。
いま、作れてよかったアルバム『uku』
素晴らしい10年間を過ごされた中で、今作『uku』は、その10年の証のような作品です。拝聴して、仕上がりに圧倒されました。藤原さくらというシンガーソングライターの血が細部まで通っている、本当に凄まじい作品でした。

藤原:ありがとうございます! 嬉しいです。
まずは、『uku』に込めた藤原さんの思いからお聞かせください。
藤原:前作『wood mood』というアルバムは自主レーベルの「Tiny Jungle Records」から2024年にリリースした1発目のアルバム。自分でまた一から何かをやっていこうという時に制作して、自分のやりたいことができたし、達成感もありました。ただ、コロナ禍が落ち着いてきたあたりから身体に色々症状が出始めていて。
耳や喉の不調。
藤原:はい。まず、歌っているときに、耳が塞がるような症状が出始めて、「ん?」という違和感から。原因も分からないし、「なんでこんなことになるんだろう?」みたいなことが相次いで起こって、ライブをすることがストレスに感じるようになったんです。「ライブ中また耳が聞こえなくなって、ピッチが取れないかも。嫌だな」と思いながら。でも、出来ないこともないからライブは続けてましたね。
不安を抱えながら歌うことはとても辛いですよね。
藤原:そのまま続けていたら、次は発声障害になってしまって。私の場合は、一定の音になると急に息が漏れすぎて、音が発声できないものでした。原因が分からないまま続けていくことがすごく不安だったし、父は異変に気付いたようで、「大丈夫?キー高い?」と心配していて。そんな状況が続く中で音楽が楽しいと感じなくなっちゃったんですよね。いい曲は書けたし、納得はしているけど、歌えない。こうやって症状が出てしまうということは、音楽が向いていないのかもしれない。制作することは好きだから音楽は続けたいけど、ライブはもう止めようかなとも思った。ここまで頑張ってきたし、一旦区切りをつけようかなと、そういうところまで行っちゃったんです。
それは、誰かに相談されたり?
藤原:マネージャーさんともお話して、「休んだ方がいい」ということになって。少し長い期間、お休みを頂いた時、やっぱり私は歌うことも好きだと実感した。だから、やり方や考え方を考えようと思ったんです。例えば、高い声は出ないけど、低い声なら他の人よりも出る。今自分が持っているものや、こうなったことで気付けたことがたくさんあるから、全然マイナスな部分だけじゃないと思えて。その瞬間からどんどんポジティブになっていったんです。
明かりが差した瞬間があったんですね。

藤原:はい。自分がこうなったのには理由があったんだと思えたし、自分が本来持っているものや素材をもっと活かした歌い方があるかもと考え始めた時、ジア・マーガレットという失声症を克服したアーティストを教えてもらいました。彼女は声が出ない時にでもアルバムを制作されていたんですけど、彼女のアルバムを聴いた時、人は生まれればいつかは死ぬように絶対に不可避なことってあるし、自分の努力だけじゃどうしようもないような時に考え方を切り替えて、今の自分に何が出来るのか捉え直すことが出来るようになったというか。
前作『wood mood』が森の中に迷い込んでいくというコンセプトで作ったのですが、『uku』を作るときは、その森をかき分けて抜けた先にビーチがあった。そういう絵が浮かんだんです。今作も石若駿さんと制作をご一緒したんですけど、石若さんには、「今まではすごく寒かったから服を着込んでいたけど、それを脱いで、ただ自分のありのまま、薄着で、苦しいも悲しいも嬉しいも楽しいも全ての感情を味わえる、そんな作品が作りたいです」というようなことをメッセージしたんです。
すごく解放感がある作品に仕上がっていると思いました。おっしゃる通り、プロテクトされていたものを剥いで、自由に踊っている印象。
藤原:ジャンルもトロピカルなテイストのサルサだったり、パーカッションが効いているようなもの、あとはレゲエとか、自分の今のムードのプレイリストを石若さんに聴いていただいた上で「この曲はこういうリズムどうですか?」など、やりとりをしながら、アルバムを完成させました。
気持ちが晴れやかになったからこそ、解像度の高い制作が出来たのでは?
藤原:そうですね。『uku』は例えるなら波のようなアルバムです。最初はパカーンと音像的にも開けているんですけど、インタールードの後は深海に辿り着いて、言葉では説明できないような不思議な景色を見る。陰陽ってバランスがあって、どっちも別に悪いものではないというか、ずっと明るいだけが正解ではないし、私もすごく波がある人間なんです。ポジティブな日もあれば、「あ、無理かも」っていう日もあるわけで。そんな波の中で制作したアルバムだったので、それを曲順でも表現したいなと思ってました。
『Interlude』からの『深海』が潜るスタートというか。そこからまた浮上して、明るい方へ向かっていく感じ。
藤原:まさに、そうですね。
お話を聞いていて、健康的というか、音楽作る上でもメンタルの上でもすごく健康的なアルバムだなと思いました。だからこそ音の節々から藤原さんの血を感じることができるのかなと。
藤原:あはは(笑)。ありがとうございます。
サウンドがラテンやジャジーな雰囲気になったのは、藤原さんの今のモードがそうだったからですか?
藤原:そういうモードだったのはあるかもしれないですけど、この地域の音楽というのは限定させたくなくて。「今回はキューバです!」と銘打つにはゆかりがなさすぎますし……(笑)。だから今作のサウンド感は私の理想郷。どこか分からないけど、すごく暖かくて、過ごしやすいところに出たな、みたいな感じにしたかったんですよね。やっぱり南米のリズムってすごく難しくて、現地に住んでいるからこそ出せるバイブスみたいなものってあると思うんです。そこを学びたいと思ったんですけど、座学でやるものではないと思って、サルサダンスを習ってみたんですよ。
おお! 実際にやってみるという藤原さんの性格ですね。
藤原:そう、何回か通って踊ってみました。キューバ人の先生が一緒に踊ってくれるんですけど、やっぱり難しくてミスをして「すみません!」と謝ってしまうことも多くて(笑)。すると、「謝らないで!」と言ってくれるんですよ。「間違えてもすぐ次のステップを踏めばいい」と言われて、確かにその通りだなと。やったことないんだから出来ないのが当たり前だし、自分は何を謝っているんだろうと思った。そういう度量というか、軽やかさというか、そこにすごく感銘を受けたんですよね。こういうゆったりした時間が今の自分に足りてないピースだったんだと気付けた。
バランス感覚というか。
藤原:バランスってやっぱり大事ですよね。こういうふうになりたい!と真面目な向上心を持った上で、且つものすごく適当な部分も持っている人ってバランスがいいなって思うんですよ。いろんな経験を経て「このエッセンスが今の私には足りてない、足そう」みたいなことを意識するようになった。今回の制作はいろんな学びがありました。
藤原さん自身のマインドのためにもこのアルバムは必要なものだった。
藤原:今までは、「あれもやってこれもやって」と結構ジャンルレスな音楽を1枚にまとめることが多かったんです。でも、『uku』のように今自分が伝えたいメッセージを、いろんな角度から歌っているみたいなアルバムってあまりないし、なかなか出せないものだと思うんです。今作れて本当によかったアルバムですね。
ここに辿り着いたよと言える1日に
その上で、武道館公演が間近に控えていることも運命的な感じがします。メンタルが整った上で10周年を締め括ることが出来る。

藤原:今までリリースした曲を今の自分がやるとなると、アレンジも含めてやっぱり変わる気がしていて。今回はジャズのメンバーたちなので、きっと昔の曲もすごく面白いアレンジになると思いますし、「ここに辿り着いたよ。10年間いろいろあって、ここに来たね、今日」という日にしたいです。
ドラムはもちろん石若さん?
藤原:はい! 実は石若さんも武道館は初らしくて!
ええ?! そうなんですか!
藤原:意外すぎますよね(笑)。石若さんの初武道館を奪えるのは、嬉しいですね(笑)。
めちゃくちゃ楽しみですね。ちなみに藤原さんにとって武道館ってどんな場所ですか?
藤原:お客さんとしてかなり観に行っている場所なんですよ。最近も、エリック・クラプトンのライブを観に行きましたし、今作でご一緒した安部勇磨さんのnever young beachのライブも観に行ったし、本当に大きな場所すぎて……。事務所のライブで一度武道館には立ったことがあるんです。当時、大きいんだけどお客さんとの距離が近いことを体感していて。他の会場とは異なる、他にはない場所だと思います。緊張すると思うけど、今この状態で立てる予定なのが嬉しい場所ですね。
どんな音を鳴らすのか、すごく楽しみです!
藤原:ぜひ、遊びに来てください!!
地続きに存在している、思い出や想い
今年は年始からトピックが多い藤原さん。ここで少し俳優・藤原さくらについてもお聞きします。2月27日から新宿武蔵野館ほか全国順次ロードショーとなる『結局珈琲』で主演を務められますが、今作の撮影はいかがでしたか? 会話劇が癖になりました。

藤原: 2日間で撮影したんですけど、本当にあっという間の撮影で。頭を空っぽにして観られる作品だと思っています。この作品は、実在する「こはぜ珈琲」移転するということで制作された映画なのですが、台本にも「場所は延長線上に存在してる」と書いてあって。
それこそ武道館ってビートルズをはじめいろんなアーティストが立ってきた場所で、歴史を受け継ぎながら今も存在している。
最近、トム・ハンクスの『HERE 時を越えて』を観たんですけど、それも定点カメラで恐竜の時代から現代まで、同じ場所を行ったり来たりする作品で、一人の家族が幸せに暮らしたりもするし、離婚したりもするしというのをずっと描いている作品だったんですけど、『結局珈琲』もこはぜ珈琲という場所があって、そこは移転しちゃうけど、記憶は残り続けて、なんなら次の場所に移行していく…ということを描いている作品というか。
そこがもし更地になっても、全然違う場所になっても、そこにあった思い出が消えるわけじゃない、一見すると寂しいことだけど、少しも寂しいことではないと思える。自分の中でもタイムリーな感情だったからこそ、演じていて楽しかったですね。
俳優としての活動は、藤原さんにとってこうアーティスト活動にこうどういう影響とかもたらしていると思いますか?
藤原:刺激になりますよね。やっぱり、その場所でしか出会えない人たちがたくさんいるわけじゃないですか。今もこはぜ珈琲の店長さんと一緒にファンクラブの企画でブレンド珈琲を作ったりしているんですけど、そういうことって音楽をやっているだけだったら絶対に経験してない。話す機会がなかった人たちとお話をして、一つのものをみんなで作るのはすごく楽しいことですね。
音楽は自分が監督っていう気持ちで作っていますけど、誰かの作品に、自分が一つのピースとして参加できるっていうのは、いつも刺激的ですし、そこで感じたことで曲になります。相互作用というか。音楽でやってきたことも芝居に生きていると思うし、楽しんでやっています!
どちらも必要なものであると。
藤原:そうですね!
では、最後にLotus恒例の質問でインタビューを締めたいと思います。今作『uku』を花や植物に例えると、どのようなイメージになりますか?
藤原:難しい質問ですね(笑)。どうしましょう〜。でも、儚いというより、強いイメージで、見たことのない、南の方に生えている謎の植物っていうイメージはすごいあったんですよ! 多肉植物みたいなイメージかな。湿気のある地帯で変な模様が入っている、日本ではあまり見ることができない、謎の植物ですね(笑)。

TEXT 笹谷淳介
PHOTO Kei Sakuhara
読者プレゼントの応募方法
\藤原さくらのサイン入りチェキを抽選でプレゼント!/
— 応募方法 —
①Lotusの公式X(@lotus_magic_d)をフォロー
②Xで上のアカウントからポストされる対象ポストをリポスト
【応募締め切り】
締め切り:2月27日(金)
公式Instagramでも実施中!!
たくさんのご応募お待ちしております!
X (Twitter)
“クリエイターの言葉を伝える”エンタメ総合メディア「Lotus」始動!アーティストやクリエイターが放つ純粋な言葉の魔法をお届けします。
— Lotus編集部 (@lotus_magic_d) April 1, 2024
ここだけでしか見れない独占インタビューやオリジナル記事も続々登場!
▼https://t.co/PrO5UQxDrF #Lotus